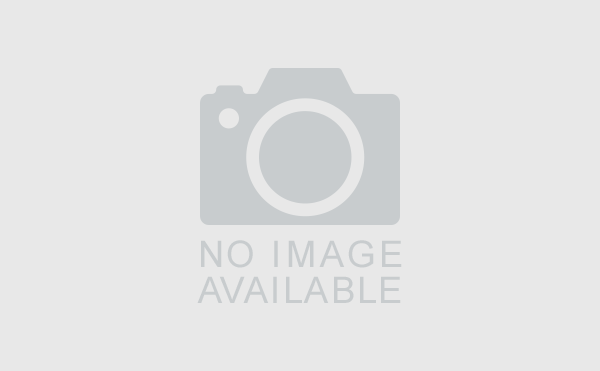肩こりと“噛み合わせ”の意外な関係
~歯の食いしばりや顎関節のズレが首肩こりにつながる~
首肩こりと “噛み合わせ” には深いつながりがあります。
歯の食いしばりや顎関節のズレは、首肩の筋肉にまで影響を与え、慢性的なこりを生み出しているのです。
■なぜ噛み合わせが首肩に影響するのか?
1. 顎と首は筋肉でつながっている
顎を動かす筋肉(咬筋・側頭筋)は、首や肩の筋肉(胸鎖乳突筋・僧帽筋など)と連動しています。
そうすると、私の視点ではもっとその下、脚の方からも影響していると言えます。
食いしばりや歯ぎしりで顎が緊張すると、その緊張は首や肩に波及し、こりを引き起こすことは大いに関係しています。
2. 姿勢への影響
噛み合わせがズレると頭の位置が傾き、姿勢が崩れます。
頭はボーリング球ほどの重さがあり、そのバランスが崩れると首肩に余計な負担がかかります。
もしかすると、姿勢のアンバランスからくる食いしばりの可能性もあります。
3. 神経と血流の圧迫
顎関節の周囲には神経や血管が集まっています。
顎の緊張が強いと、頭部や首の循環が悪化し、頭痛・耳鳴り・肩こりを助長します。
顔面の特徴で言えば、エラが張る、たるみ、むくみ、くすみ、顔の歪みなどに影響します。
■食いしばり習慣がもたらす悪循環
- 睡眠中や日中に無意識で歯を強く噛んでいる
- 集中しているときに奥歯を噛みしめている
- 朝起きると顎が疲れている
- 朝からこめかみ辺りが痛む
これらは全て「ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)」と呼ばれる習慣。
顎の筋肉が常に緊張し、首肩のこり・頭痛・顎関節症へとつながります。
■噛み合わせと肩こりの“相互関係”
- 噛み合わせのズレ → 顎の緊張 → 首肩の緊張
- 首肩のこり → 頭の位置が崩れる → 噛み合わせがさらに乱れる
つまり「どちらが原因か分からない」悪循環に入りやすいのです。
■まとめ|肩こりの原因は「噛み合わせ」かもしれない
肩こりを何年も抱えているのに改善しない方は、筋肉や姿勢だけでなく 歯と顎のバランス にも注目すべきです。
- 食いしばり → 首肩こり
- 姿勢の崩れ → 噛み合わせの乱れ
- 両者の悪循環 → 慢性化
「歯は歯、肩は肩」と切り離して考えてしまうと、本当の原因を見落としてしまいます。
首肩こりを根本から改善するために、ぜひ“噛み合わせ”という視点を取り入れてみてください
~ 私の想い ~

LaLa鍼灸サロンの髙中沙樹です。
皆様の健康に寄り添い、これからの生活をより明るくするためのサポートをしております。
”このままではいけない”そう感じて行動を起こした女性が集まるサロンです。首肩こり専門と謳っていますが、多くの場合、それはきっかけにすぎません。
・なぜ首肩がつらくなるのか?
・なぜたかが首肩こりにそこまで聞かれるのか?
・なぜたかが首肩こりを改善させる必要があるのか?
それは、首肩こりは体からの静かなSOSだからです。
自分を後回しにしてがんばり続けた日々、そのすべてが首や肩に現れているだけ。
だから私は、「本当の原因」と向き合うことを大切にしています。
つらさをごまかすのではなく、“自分を大切にする”という視点から体を見直すことが、生活を変える第一歩です。
もし、あなたも「そろそろ自分の体とちゃんと向き合いたい」
そう思ったなら、私はあなたの力になれます。
LaLa鍼灸サロンで、あなたの人生がもう一度、軽やかに動き出しますように。